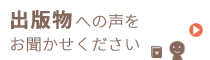- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- オーストラリア―クイーンズランド
オーストラリア―クイーンズランド
二月七日、クイーンズランド、ケアンズ空港に午前四時十分着。成田から約七時間三十分のフライト。入国審査後、65km離れたポートダグラスの宿泊地ラディソン・ロイヤルパーム・リゾートに向けてまだ明けやらぬ国道一号線を北上する。この道路は別名キャプテン・クック・ハイウェイと呼ばれているが、片道一車線で大型バスがやっとである。日本ではさしずめ二級国道というべきか。海側の右手沖合い20kmから100kmには、世界に名高いグレート・バリア・リーフがある。珊瑚礁が防波堤の役割をしているためか、トリニティー湾は波静かで内海の感がある。
ポートダグラスまでの植生は、ユーカリ主体の疎林が続き、あまり見るべきものがない。ユーカリはオーストラリアには五百から六百種あるといわれ、現地ではガム(Gum)・ツリーと総称している。これはオーストラリアの全樹木の90%を占めている。これに次ぐ木はワトルと呼ばれるアカシアで、カンガルー、エミューとともにオーストラリアの国章にも使われている。
ユーカリといえばコアラだが、クイーンズランドは暑過ぎて生息していない。数多くあるユーカリのうち、コアラの食べる木は四から五種であるという。コアラとは原住民アボリジニーの言葉で「水を飲まない」という意味である。第三紀以来孤立した大陸であるオーストラリアは特異な動植物相をもち、卵生の原始的な哺乳類であるカモノハシやハリモグラなどが生息する。カンガルーやコアラを代表とする有袋類は百五十種以上いる。
オーストラリア大陸の面積は7,682,300 km2で、日本の国土の20.34倍の広さがある。平均高度はわずか330mで、世界の大陸の中で最も平坦である。広大な国土の71%が年降水量500mm以下の乾燥地域で、人口は約千七百万人で東京首都圏とほぼ一緒。国土の85%が人口密度1km2当たり1人以下である。
オーストラリア大陸の存在はギリシア時代すでに予言されていたが、ヨーロッパ人の発見は遅く、タスマニア島とニュージーランドを発見したオランダ人、アベル・タスマンもなぜか発見しておらず、一七七〇年にイギリス人のジェームズ・クックが大陸の東岸を発見し、沿岸を探検してイギリス領を宣言した。この後イギリスは流刑の地として定めた。一七八八年一月、最初の流刑者957人が送り込まれ、それは一八六八年まで続いたが、この間各地の入植者も増えた。一八五一年、金鉱の発見で人口は急増し、五つの自治植民地(州)が成立した。そして一九〇一年に、オーストラリア連邦が結成されたのである。
ポートダグラスのラディソン・ロイヤルパーム・リゾートは街から少し離れた場所にあり、国道にはその名の通り、ダイオウヤシ、アブラヤシの並木が植えられている。植生見学もさることながら、朝食前なので空腹と疲れに耐えられず、部屋割りが決まるとまずは食事をとった。終了後は各長屋風コテージにて一服といっても、長旅の疲れでシャワーを浴び、昼近くまで仮眠するものが多かった。今回の旅の参加者は、インドアグリーン協会のカレンダーロケ一行と植物研究会の面々で総勢19名であった。みな旅慣れたものばかりで気楽であるが、目的のカレンダーの標的は逃すことができない。
今は雨季で晴れ間が勝負となる。室のカーテンを開け、行動開始。ベランダに一歩出ると30℃以上の熱帯の空気である。庭にはホテルが建つ前からのものと思われるユーカリが二、三本立っていた。白茶色の樹皮はカンナクズ、いやトロロコンブ状で、それが何層にも幹についている。オーストラリアではブッシュ・ファイア(野火)が多く、前年(一九九七年)暮れのシドニー郊外の大山火事は記憶としてまだ新しい。現地では野火は珍しくなく、樹木自身も断熱効果のある樹皮へと適応変化してきた。乾燥期にユーカリは揮発性の物質を放出して、野火の原因作りも自らしている。ライターでタバコに火を着けようとしたら周囲の空気がボッと燃えだした話を聞くが、あながち誇張とも思えない。ユーカリのように葉や枝を燃やすことによって、次代の植物と己自身のカリ肥料として利用するもの、またバンクシアのように、500℃以上になると硬い殻から種子を弾き出すことができるものなど、火を利用して生きているのは人間ばかりではない。
さて室の前のユーカリだが、幹の分岐点を中心として、ガガイモ科のマメヅタカズラ属(Dischidia)が着生し、径二cmほどの多肉質の葉が連なる様はあたかも樹上のネックレスといったところだ。さらに高い小枝には根元がタマネギ状に肥大した植物がある。アリノトリデ(Myrmecodia tuberosa)と呼ばれているアカネ科の植物で、肥大部はアリの巣になっている。マメヅタカズラもアリ植物で、これらの植物はアリと寄主と三者の共存関係にあるので、採集しても人間だけの管理下での栽培はむずかしい。
ここのリゾートホテルはゴルフ場、テニス場などのスポーツガーデンがある。これらを含めるとかなり広大な面積で、正面入口には道路に沿ってサトウキビ運搬鉄道があってディーゼル車が走っている。現在は農閑期のため観光用に一時間に一本程度運行しているだけである。
ホテルの庭はよく整備されてヤシの種類も多く、特にクイーンズランドはユスラヤシの原生地ということもあり数多く使用されている。ユスラヤシ属(Archontophoenix)はオーストラリアに四種あり、代表種ユスラヤシ(A. alexandrae)は、後日訪れるデントリー河畔のアレクサンドラ山が原生地で、別名アレクサンドラ・パームという。日本では無霜地帯で露地栽培ができ、0℃が一冬に二、三回ある程度までなら越冬できる。ユスラヤシの中でバンガロー・パームと呼ばれるA. cunninghamianaは、特に幹高2、3mぐらいではマニラヤシに大変よく似ているが、高さ20mにもなり、幹の環紋の鮮やかさ、葉柄のつき方の疎らさなどで見分けることができる。
二月八日、ポートダグラスを離れいよいよ北部のデントリー川国立公園に出発。車はベンツの20人乗り四輪駆動でタイヤも大きく、悪路を走るため車高が高い。まわりにサトウキビ畑の広がる国道を北上する。
○デントリー・クルーズ
デントリー川に着いた。ここでは川岸の植生を見せるリバー・クルーズがあり、われわれもトライすることとなった。川岸に数件ある民家の庭には、赤いサンゴ状の花を咲かせているゴウシュウアオギリ(Brachychiton acerifolius)の大木があった。パパイヤに似た葉は開花期には落葉して丸坊主であるが、枝のあちこちに笹の葉でくるんだような大きなチマキ状の物が付着している。これは樹上のアリの巣である。このアリは樹木を選ばず巣を作り、うっかり傍を通ったり、触れたりすると大変で、やたら落ちてきて、攻撃されひどい目に遭うので要注意である。クイーンズランドでは色々なタイプのアリがおり、湿度の高いジャングルでは樹上に土を材料としてアリ塚を作るもの、腐朽木に作るもの、同種でも比較的乾燥したアサートン高原では地上に巨大なアリ塚を作るものもあった。ガイドの説明では口に酸味が欲しくなった時、アリをつかまえて舐め、一時の清涼剤として利用する種もいるとのことで、実演していた。
リバー・クルーズは、マングローブの観察が主であるが、ワニも見ることができる。しかし、全行程で体長40から50cmの幼ワニを一匹見ただけであった。ここは海から6km、ちょうど満潮のためマングローブの奥まで水が入り、ワニも奥の方に移動したらしく、大型のものは目にすることができなかったのである。
川岸には、トウの一種(Calamus moti)やフトモモ科のミズレンブ、ヒルギ類、サガリバナ、ユーカリなどが生え、中でも丈が抜きんでるのはユスラヤシとブラック・パーム(Normanbya normanbyi)である。ブラック・パームの小葉は密で、まるでタヌキの尾のような形態である。幹の外皮は硬く、切り倒すのにチェーンソーも効かない。建材用としての耐久性、耐湿性は抜群で、原住民は家の柱や橋などに用いている。この地方の固有種である。
ユーカリの大木の繁茂した場所にはフルーツコウモリが群生し、一種異様な雰囲気である。動物食のコウモリは夜行性であるが、果実を食べる種は日中でも飛翔する。古くから、獣肉のない太平洋諸島では、唯一の肉としてフルーツコウモリを食べる習慣がある。マリアナでは猟期が決められ、種の保存を図っているが、密猟が多くて激減の一途をたどっているそうだ。最近では北マリアナの無人島アナタハン、サリガン、ググアンなどの島から獲ってくる話も聞く。七、八年前までは、普通にスーパーストアに冷凍されたものが置かれていたが、現在ではその姿を見ることができない。日本では食べる習慣はないが、オオコウモリ属ではオガサワラオオコウモリとクビワオオコウモリの二種が生息し、後者の亜種としてヤエヤマオオコウモリ、ダイトウオオコウモリ、エラブオオコウモリ、オリイオオコウモリがいる。いずれも天然記念動物に指定されている。
デントリー川以北の川には橋がなく、大きな川はフェリーで渡る。われわれの乗った大型四輪駆動車はフェリーで船着場に先回りして待っていてくれた。昼食はこれより三十分離れた山間のレストランで食べた。メニューは肉、魚のどちらかを選び、魚は白身のムニエル風で、まあまあの味であった。食後レストランのオーナーが裏山にある滝までわれわれを案内してくれた。崖沿いの細道は蚊も多く、足元悪く、正にジャングルロードである。ここにはオーストラリア北部ジャングルの固有種、ザミアファーン(Bowenia spectabilis)が自生している。朝鮮ニンジンのような幹は地中にあり、二、三枚のルスクスに似た葉を地上部に展葉するもので、現地では切葉としてフラワー・アレンジメントに使われている。小葉はナギの葉によく似て、光沢があり、切っても数週間はその新鮮さを保つという。その名の通り、新芽はシダ植物のようなワラビ状でソテツ科の中では最小のものかもしれない。形態的にシダ種子類からの進化を最も感じさせる植物であった。
車はこの日(二月八日)の宿泊地トリビュレーション岬の「ココナツビーチ・レインフォレスト・リゾート」に向かう。途中アレクサンドラ山麓から様相がすっかり熱帯雨林に変わる。50から60mの高木層、蔓性植物、ゴウシュウクロヘゴが出現し、リュウビンタイなどのシダ植物が林床を占める。明日はこのジャングル・トレッキングを予定している。ここの部屋はログハウスタイプで、三室が一つになった長屋である。湿度が高いので皆高床式になっている。メインレストランは海岸の近くにあり、湿地帯の木道を歩いていくことになった。夜にはカエルの大合唱で騒がしい。食用蛙を含めて何種類か棲んでいるらしく、日本の田圃のカエルとは、トーンやボリュームが異なり、かなりうるさい。200から300坪あるレストランは中央部が吹き抜けで、天井が高く、中に元々から自生していたであろう高さ5、6mはあるタコノキの一種(Pandanus pedunculatus)が床をくりぬいて取り込まれている。
庭先からテリハボク、モクマオウ、クサトベラなどの林を抜けると、おだやかな砂浜に出る。砂浜には波状に打ち上げられた漂流物が堆積し、そのほとんどは枯れた小枝や海藻の類で人工的なものは見当たらない。堆積物の中に黒く光るオタフク豆の親方ともいえる径5cmばかりのモダマ(Entada phaseoloides)の種子があった。モダマを海岸で拾った話をしたところ、後は全員でモダマ拾い合戦、戦果はおそらく50個以上あったと思われる。
モダマ以上に目についた漂着物は、ホウガンヒルギ(Xylocarpus granatum)の種子である。このセンダン科の植物は、高さ6mになり、マングローブを形成する。特徴は板根が発達することで、この板根は低いが、タチウオをくねくねさせた形状で、よく伸びる。果実は円形で、径20cm、砲丸状である。日本での自生はなく、タイ、ミャンマー、マレーシアなどの東南アジア、太平洋諸島に分布している。材は硬く、耐久性、耐水性、耐虫性が大で、家具、パイプ、ボートや船のキール、木釘などに利用されている。果実は円形から熟すると四裂して、種子は三~四稜角の不規則円錐形で、海岸に流れ着いたものは、何の種子だか最初は解らなかったが、付近のものを組み合わせると球形になり、やっとホウガンヒルギの種子だと気がついたわけである。
デントリー・クルーズでリンゴ大の青い若い果実を成らせた木を、ガイドはソルトアップル(塩リンゴ)と説明していた。そのときは聞き流していたが、やっと謎が解けたわけであった。まあ物事、体験による解明ほど楽しく確かなものはない。ホウガンヒルギの果実を見るのは稀でまことにラッキーである。このリゾート地は日本の何でも開発式のイメージとはまったく異なっている。われわれが泊るログハウスは、半径100mの円周状にジャングルを切り開いたわずかばかりの土地に、小径に沿って十軒ばかり建てられている。円の中心部と外側は手つかずの自然で、体長1m以上のイグアナやヘビなどの野生動物が出没する。高木に混じり、大きな円形の羽状葉を広げているのはウチワヤシ属のLicuala ramsayiで、高さ6から18mになる固有種である。ウチワヤシの仲間は東南アジア、オーストラリア、ニューギニア、インドに87種あり、属名のリクアラはマルク(モルッカ)諸島の俗称に由来する。この仲間は日本ではマルハウチワヤシ(L. grandis)一種が観葉植物鉢物として生産されている。
○ジャングル・トレッキング
二月九日。今日はいよいよジャングル・トレッキングである。宿泊地から戻る形で南に数km、海岸沿いにその降雨林はある。湿地帯には木道が敷かれ、一応道以外の立ち入りは禁止されている。フトモモ科、マメ科、ユーカリなどの高木が天を覆い、林床は薄暗い。樹上に鳥の巣状に大きな塊を形成しているものが見られる。樹冠着生シダでバカマウラボシの仲間(Drynaria sparsisora)やネフロレピス、シマオオタニワタリなどが作るもので、このような着生植物は葉の間に上から落ちてきた葉や小枝を集めて栄養分をとり、腐食が進んでくるとランやコケがさらに着生してコロニーを作り、「空中庭園」の形態をとるものもある。ここには大型のヤシは生えていない。高さ1.2mの小型のヤシは、高性テーブルヤシの葉をコンパクトにしたようなリノスパディックス(Linospadix)で、この属はオーストラリアからニューギニアに11種あるが、日本での記載図書は見つからない。長さ30から50cmほどの花柄を下げ、黄色から赤色に熟す果実は房状で美しい。一見食べられそうだが毒があるとのことであった。この密林にはL. minor、L. microcaryus、L. monostachyos、L. palmerianusほか5種があり、形態も単幹、株立ち、羽状葉やヒメテーブルヤシ(Chamaedorea tenella)のような幼葉掌状葉などさまざまで、鉢物にすれば小鉢から大鉢まで幅広く使えそうなヤシである。大木には太い蔓が絡まり、葉ははるか上空であるので、蔓性植物の同定は樹冠の上まで行かねばならない。この辺に野生する動物はワニの他にヒクイドリがいる。繁殖期になると気が荒くなり、人間にまで攻撃をかけることもあるそうだ。この大型の鳥はダチョウと同じく、飛ぶための羽根は退化しているが、脚力に優れ、これにキックされると相当のダメージを受ける。聞いた話では学校に通う男の子が同じ鳥に三日続けて攻撃され、たまらず父親がライフルで仕止めたとか。ワニは川に棲むものと海に棲むもの二種がおり、この辺はやたらに生息していて、川や海での遊泳は禁止されている。この話をすると「海にワニがいるの?」とびっくりされるが、パラオの海、フロリダの海にも棲んでいるので珍しいことではない。海にはワニがいるほか、デンキクラゲ(カツオノエボシ)が岸から500mの沖合いまで、時期によっては大量発生するので、大自然のきれいな海でもネットを張った囲いの中でなければ泳ぐことはできない。尤も何キロも沖の小島やリーフにはこれがいないので、良いダイビング・スポットも無数にある。かといって安心は禁物。地元オーストラリアの現職大統領がグレート・バリア・リーフでダイビング中に行方不明となり、ついに発見されなかったことも確か数十年前にあった。ワニはいなくても、ワニザメやウミヘビ、ダツ、ウツボなど、人間を攻撃するものも多数いるのである。こんな話は観光パンフには一切載せられていない。オパールとコアラの国、女性が好むイメージで宣伝しているだけである。
マングローブを形成している木はヒルギ類、サガリバナ、サキシマスオウノキ、ホウガンヒルギなどで、板根や気根、支柱根にはそれぞれ特徴があり、変化に富んだ形態は見ている者の興味を誘う。ここのマングローブは高さ10から15mでさほど高くない。マヤプシキ(ハマザクロ)などの大高木になるものが生えていないためと思われた。
○真珠貝の話
昼食は、最北の地トリビューション岬のつけ根にある小川にて弁当をとることになった。ここはオーストラリア大陸の右の角といわれるヨーク岬半島の中程で、さらに500km北上するとヨーク岬があり、沖合いにはかつて真珠の島として有名だった木曜島がある。明治四十一年、日本より真珠採取移民が送り込まれ、南洋真珠(南洋玉)のメッカとなった。南洋玉は真珠の中でも最大でシロチョウガイ(Pinctada maxima)からとれ、英名ゴールドカップ、パール・オイスターなどと呼ばれている。ちなみに日本での真珠養殖に使われている貝はアコヤ貝(P. fucata martensii)で玉は小形である。養殖に使われている貝のほとんどが、ウグイスガイ科(Pteriidae)のチョウガイ属(Pinctada)で約8種が利用され、半円真珠にはマベガイ(Pteria penguin)が使われている。ウェスタン・オーストラリア州北部のブルーム(人口3,800人)の町は、一八九〇年から一九三〇年に木曜島と並び真珠貝採取で栄え、最盛期の一九一三年には、ダイバーとしての日本人が1,166人移住していたという。このほか、ピルバラ地方のコサックなどには当時活躍した多くの日本人の墓があるという。食事後は小班に分かれ、ジャングル歩きや川で泳ぐもの、昼寝をするものなど、思い思いの行動をとった。われわれはジャングルに入った。道らしい道もなく茨や刺のある植物が多く、何度も行く手をはばまれた。トウの一種(Calamus radicalis)は本体の刺だらけに加えて、細長い5から10mにもなる刺だらけの蔓をやたら伸ばしている。この蔓はトウが他者について登攀するためのトラ(園芸業界用語で何かを立てる時に倒れないように四方に張るロープやテグス)の役目をしているもので、釣り針状の刺は一度絡まれると皮膚にくい込んでなかなか抜くことはできない。そんなわけでついに陸上歩行を断念して、川の中を進むこととなった。この川の水は濁っておらず飲んでも害がないというが、ともかくワニの影におびえながらの河中行であった。
午後からの行動は海岸にて一服。砂浜であるが、岬のつけ根部分には人頭大のゴロ石の海岸があり、その部分だけにヤエヤマヒルギ属のフタバナヒルギ(Rhizophora apiculata)がかなり広い純林を形成している。ゴロ石は海が荒れた時に運ばれたものがヤエヤマヒルギの支柱根により捕らえられて固定されたものと思われた。帰路パンノキの果樹園でカレンダー写真の撮影をした。ガイド兼運転手はジャックフルーツ(パラミツ)として説明していたが、私たちはブレッドフルーツでパラミツでないことを説明した。なんとか理解してもらえたようだが、オーストラリアでは両種ともあまりポピュラーでないようである。パンノキは長い間太平洋諸島の重要な主食として利用されてきたが、近年米や麦などの美味しい主食に代わってしまい、徐々に食べる習慣もすたれている。山間の方から黒い雲が広がり、あっという間にスコールである。この地方はまだ雨期の最中で一ヶ月300から400mmの降雨がある。夜には決まってバケツをひっくり返したような豪雨があり、天井も抜けんばかりの正に「雨車軸の如し」、熟睡していても目が醒めるほどである。
今夜はご当地最後の夜ということで、夕食はシーフード大皿盛りに、仮設屋台で焼かれるワニの肉、羊肉、魚肉、取って食べ放題の果物の山、ワイン、ビールの壜が並ぶ。ムール貝やゾウリエビ、アサヒガニ、ガザミの残骸がテーブルの上にうず高く積まれ、旅の話題に花が咲く。小食低燃費でよく動く筆者にとって仲間達の胃袋は驚異であった。中にはさらにカレーライスを注文する豪傑もあり、これで筆者も同じ旅行費用とはとても納得できないとつくづく感じる一場面であった。
○ワライカワセミとツカツクリ
二月十日、午前八時三十分、ケアンズに向けて出発した。途中ポートダグラス郊外の動物園に寄る。ここには半径50m、高さ10mの巨大な檻があり、その中に多数の植物が植栽され、鳥が放し飼いになっている。鳥の多くはインコの仲間で赤、紫、緑、黄などの原色が鮮やかである。よく人に馴れて、軽食に出されたサンドイッチなどをついばみ、人々の肩や頭に恐れもなく止まり、餌をねだっている。オーストラリアといえばワライカワセミだが、ここには狭すぎて飼うことができないのであろう。姿はなかった。昨日泊ったレインフォレスト・リゾートでは、あの頭の毛を逆立て、長い嘴と特徴ある白に濃い茶色とコバルトブルーの羽根をもつワライカワセミに何回も出食わしている。この鳥は早朝よく鳴き、「ケタケタケタ」と人間の笑う声そっくりで森中に響き渡る。現地ではクッカバラと呼ばれている。カワセミやヤマセミと同じショウビンの仲間だが、一回り大きい。日本にいるカワセミは小魚や水生昆虫などを食べるが、ワライカワセミはトカゲやネズミ、時には体長の何倍ものヘビまで飲み込むという。狩りは待ち伏せ型で、枝の上にじーっと何十分でもあたりの様子をうかがい、草むらで動く物があると一瞬のうちに急降下して仕止める。待ち伏せの枝は決まっており、そこに戻ると、獲物を枝に何度も打ちつけて骨を砕き、殺してから飲み込むという、この仲間独特の行動をとる。
ワライカワセミは日本ではあまり知られていないが、かつてその笑い声がオーストラリアの日本語放送の冒頭に使われていたこともあり、短波マニアの間では有名であった。最近小形のヒトデカズラ(Philodendron selloum)が切葉や中鉢物として、主に八丈島から出荷されているが、その名がクッカバラ。これは先述のようにワライカワセミの現地名だが、何の関係で名づけられたか筆者は知らない。
オーストラリアには、この他にユニークな鳥が多い。その最たるものは和名クサムラツカツクリ(Mallee Fowl)で、高さ1m、周囲10mの塚を作り、30個程度の卵を生み、土や枯葉の発酵温度を利用して卵をかえすのである。塚を作る鳥は何種類かいるが、このクサムラツカツクリはユーカリ林に棲み、ヤマドリ大で足が太く、指は鋤のように鋭い。その足で地面を蹴って土や枯葉を集め、塚を作る。一蹴りで6.9kgの石を動かしたとの記録もある。巨大な塚は何代にもわたり作られ、古いものは百年経たものもあるという。30個の卵が全部孵化するのは、三から四ヶ月かかり、ヒナは発酵堆肥の中から自力で出て、その日のうちから自分で餌を採るという。この話では親はずいぶん楽しているように思えるが、孵化する間は一応抱卵する格好をとり、巣の中に絶えず嘴を入れて中の温度を確かめ、覆っている土や枯葉を調節して、温度管理をするという。
フレッカー植物園はケアンズの中心部より北約4kmの郊外にある。フレッカー湖を取りまく自然植生がそのまま観察できるよう保護されている。海岸から近いため植物園を横切る川は塩分を含み、ソルトウォーター・クリークと呼ばれ、塩水湖もある。湿地帯の植生はパンダヌス、フィクス、クロヘゴ、ニッパヤシ、トウ類、中型のヤシ(Laccospadix australasica)などで占められているが、北部の大規模な降雨林を見てきた後では格別目新しいものはなかった。コリンズ・アベニューを隔てて管理事務所のある一角は世界各地から集められた珍しい植物が栽培されている。コショウ科のピペル・マグニフィクム(Piper magnificum)はペルー原生の小低木で、つやのある葉は表がグリーンだが、裏は暗赤色で美しい。
温室内にキンバイザサ属(Curculigo)によく似たヤシ科と見られる植物があった。幹が少し立ち上がって30から40cm、葉長は50cmぐらいで、二叉に分かれた幼態の掌状葉である。ネームプレートを見ると、(ARECACEAE Asterogyne martiana)となっているので、ヤシ科に間違いなかった。ちなみに「ARECACEAE」というのはヤシ科の基準属Arecaに基づく学名で、キク科の学名CompositaeをAsteraceaeと書いてもよいのと一緒である。帰国後に調べたところ、このAsterogyneの仲間は約三種あり、いずれも熱帯アメリカ原生とあるので、オーストラリアのものではなかった。
広く刈り込まれた芝生の真ん中にチーク(Tectona grandis)の大木がある。ここのは高さ20mほどだが、40mにもなる大高木である。このクマツヅラ科の植物はインドからインドシナに分布して材には芳香があり、強度、耐久性、抗虫性が大で、心材は金褐色に暗褐色の縞模様が入る。古来より高級家具や彫刻用として利用され、根と若葉から黄褐色の染料がとれ、種子は薬用として用いられてきた。この日は昼頃より小雨となった。半端に降ったのがたたって高温高湿度で蒸され、植物園のレストランでビールをあおって早々の退散となった。昼食は港の突端にあるラディソン・プラザでとった。ここはレストラン、土産物屋などがある大きなショッピング・センターである。昼のメニューは魚と肉料理のいずれかで、副食はバイキング形式である。土産物の多くは革製品、宝石類、衣類、置物などであるが、何といっても一番の人気はカンガルーの軟らかい腹の皮の部分をプレスして作ったに違いないキンチャク袋である。もしそうならば、カンガルーはやがて絶滅してしまうと心配するのは取り越し苦労か。
今夜の宿泊ホテルは目と鼻の先のマトソン・プラザ・ホテルでトリニティー湾に面して見晴らしはよい。この湾は遠浅で一見きれいだが、海底はヘドロで泳ぐことはできない。ホテル周辺の植栽にはかなり目を引くベニバナトケイソウがフェンスに絡みついている。
トケイソウ科の植物は世界の熱帯に約10属500種があり、液果は多汁質で果物として利用されているものも沢山ある。日本にある耐寒性のトケイソウは享保八年(一七二三年)に入ってきたもので、最近では道路のフェンスやパーゴラなどで利用されている。トケイソウという和名は花を時計の文字盤に見立てたものである。属名のPassifloraは「受難の花」という意味で、花の形態をキリストの磔に見立てたということだが、異説もある。パッションフルーツとして日本で栽培されているものは五種あり、九州、四国、八丈島、奄美大島、沖縄などで作られている。これはおそらく鳥が運んだもので、動物体内を通って発芽したものは人工的に播種したものより生命力は強靱である。何年か前、筆者が講師をしている園芸職業訓練校の卒業旅行に八丈島に行ったことがあって、農業普及員の金川利夫さんの現地農産物の説明やら解説があった後に、パッションフルーツは種子を播いても立ち枯れが多く、何か対策として良い方法はないかと、逆にたずねられたことがあった。私は、種子はパッションフルーツを食べた人間の排泄物から拾って播けば、健全な苗が育つと答えたが、実際はそうも行かないだろうから手軽な方法としては鶏糞を水で溶いた中に一昼夜浸して播けば良苗が得られると説明した。植物が成らせる果物のほとんどは動物に食べられることを目的として、約一億年前から進化してきたのである。植物は動けないことを動物に代行させたのである。また種子が動物体内を通ることによって、殺菌作用、免疫性などが得られる。これらの種子は硬い皮に覆われて、未熟果以外消化されることはない。花壇にはコンロンカの仲間(Mussaenda philippica)の園芸品種で白、赤、ピンクなど、近年東南アジアを中心に改良されたものが咲き誇っている。コンロンカ属はアフリカ、インド、東南アジア、太平洋の島々に分布しており、約200種がある。日本には琉球列島にコンロンカ(M. parviflora)一種がある。
同じアカネ科のサンタンカも熱帯地方では花木として利用される。ここには園芸品種のスーパーキングが植栽されている。ホテル前の街路樹はユスラヤシに混じってピソニア(Pisonia)と見られる黄色の花が咲いている。
○クランダ鉄道
二月二日、クランダ鉄道でクランダに向かう。この鉄道は一八九一年に完成されたもので、着工から五年の歳月をかけた難工事だったという。バロンバレー沿いの山岳鉄道である。バロンの滝に代表される渓谷は正に絶景である。客車は一八八〇年に作られた木製である。車内はすべて指定席でワインやジュースのサービスがあり、約一時間半でクランダに着く。クランダは標高329m、フリーマーケットがあり観光客相手の土産物屋が軒を連ねている。まるで祭りの夜店のような賑わいで、値札はかかっているものの、交渉次第でまけてくれる。特に皮製品が安い。尤もオージー・ビーフの取り滓みたいなものだから当然かもしれない。オーストラリアの牛は全くの放し飼いで、肉は硬く、ミンチにしてからハンバーグや、形を整えて合成のステーキなどに使われる。主な輸入先は日本である。
今日は快晴で、37~38℃はあろうか。とにかく暑い。冷えたビールを探すが、酒類は離れた場所で売られているとのことで、しかたなくコーラを飲む。目をやると店先の植栽の中に真紅の花を咲かせている蔓性植物があった。ヒルガオ科のホザキアサガオ(Ipomoea horsfalliae)である。英名をプリンセス・バインといい、西インド諸島の原生種である。日本では生産されておらず、特殊な植物園でしか見ることはできない。昼食はケネディー・ハイウェイ沿いにあるレストランである。すでに観光客を運んだバスが何台も駐車している。ここ五年ほど前からの傾向で東南アジア方面は朝鮮や台湾の観光客が増えて、この日はどうやら日本人グループはわれわれだけでハングル語、広東語の渦の中の食事となった。
さて、これからはケネディー・ハイウェイを南下し、標高差800mを登りながらアサートン高原に向かう。高原が近づくにつれて、牧場や小麦、タバコ、ジャガイモなどの大プランテーションが広がり、さながら北海道のような景観になる。この頃になると単純なバスの揺れが子守唄となって、心地よく眠る者が増えてくる。アサートンの町を左折してギリエス・ハイウェイに入り、バリン湖近くに巨大なカーテン・フィッグ・ツリーがある。この木を見たさに二時間ほどバスを走らせてきたわけで、正式な学名はFicus virens、イチジク属のアコウの近緑種である。高さ15m以上の幹から無数の気根を垂らし、さながらカーテン状であるためにこの名が付けられた。
気根の発達した樹は国内では喜界島の「百の台」下のガジュマル、パラオ諸島のコロール島のインドゴムノキなどを見たが、それに勝るとも劣らずの威容である。イチジク属は世界に約800種があるが、ほとんどの種で気根が発達する。日本ではアコウ、ガジュマル、ハマイヌビワが特に気根が多い。周囲の林は高原であるためか、北部低地のジャングルに比べ高木層が少なく、高さも20m程度で低木も疎らである。蔓性植物の中にあたかもウドンコ病にかかったような薄汚れた羽状葉のトウ類があった。英名Fishtail Lawyer Caneと呼ばれるもので、葉はクジャクヤシによく似ており、長さ5から7cmになる。白熟した果実が房状に下垂して約1mになるクイーンズランド固有種である。帰路バスの運転手はこの辺の出身であり、「よい店があるので案内する」という。見渡す限り農場と牧場で、遠くクイーンズランドの最高峰バートル・ブリア山(1,612m)が見える。とにかくだだ広く人家を探すのもむずかしい。畑の細道を行くこと三十分、百二十年前から営業しているバーに着いた。日中にもかかわらず近所の農夫やらカウボーイがビールをあおっている。五十坪ばかりの店内は古いバイクや馬具などが飾られ、さながらウェスタンの雰囲気である。そこに20人ばかりの日本人が来たものだから店は超満員となった。現地の客とも仲良くなり、蹄鉄の「チエの輪」はずしを肴にビールの泡が飛ぶ。
ふと壁を見ると、来客の名刺がズラリ貼られている。漢字の名刺はない。どうやらこんな所まで日本人は来ないようで、隣で飲んでいた西花園の山本さんと筆者の名刺を仲間入りさせることとなった。いずれにしろ横書き英文の中の縦書き漢字はかなり目立つ存在となった。今回の旅は乾燥した大陸オーストラリアのイメージとはまったく異なる熱帯降雨林を目的としたもので、年間降水量2,000mm以上で育まれる降雨林はオーストラリア全土の1%にも満たない限られた場所である。乾燥地やシドニー、キャンベラなどの大都会に住むオーストラリア人は、一生に一度はこの降雨林に行く夢を持っているそうである。
すべての大陸が一つであったパンゲア大陸から、南の部分ゴンドワナ大陸が分裂を始めたのが一億八千万年前で、八千万年前にオーストラリアは南極大陸とも分離し、孤立した大陸となった。この時期は原始的な哺乳類が現れた時期で、隔離された動物は独自の進化をとげた。有袋類を始め、爬虫類も変わったものが多い。
植物の世界ではアフリカと共通のバオバブノキ、南米と共通のナンキョクブナ、約600種のユーカリ、バンクシア、イネ科のスピニフェックスなど乾燥に適した植物群がある。降雨林は狭い地域であるが、固有種が多く、一部ユスラヤシなどが園芸的に利用されているに過ぎない。熱帯雨林は人間に対してどんな有用種があるかも解明されないまま消滅してしまうものも多い。全地球の財産である熱帯降雨林が開発・乱伐で激滅している現在、毎日数百種の植物が人知れず絶滅しているという。
- 初出掲載紙:(社)日本インドア・グリーン協会発行『グリーン・ニュース』
- クインズランド植生誌No.1(グリーン・ニュース、一九九四年五月号)
- クインズランド植生誌No.2(グリーン・ニュース、一九九四年八月号)
- クインズランド植生誌No.3(グリーン・ニュース、一九九四年九月号)
『熱帯植物巡礼』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
書籍詳細
-
完売
[2000/03/25]田中耕次 著 / アボック社 / 2000年 / B6判 286頁
定価1,650円(本体1,500+税)/ ISBN4-900358-51-7
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』